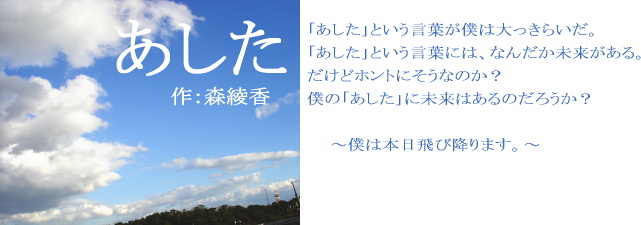|
|
| とある高層ビルの屋上に似つかわしくない一人の少年がいた。地べたよりもずっと青空に近いソコ。少年は、屋上の高いフェンスに指をかけ、ただならぬ表情で地上を見下ろしていた。 足もとには、一通の白い小さな手紙と丁寧に揃えられた白いスニーカー。少年は休日でもないというのに、学生服を着ていなかった。やや伸びがちの髪の毛にしわっぽいTシャツ、そして、くたびれたジーンズ。顔は青ざめ、唇がカサカサに乾ききっていた。白く粉を吹いた唇をしめらせるように、赤い舌先で何度もなめつける。 「思いの他、高いな・・・・」 かすれた声で少年は一人つぶやいた。フェンスに指を立て、何度もひっぱり強度を確かめてみる。小さく乾いたフェンスのすり音が辺り一帯に響いた。少年は意を決っし、フェンスに右足をかける。フェンスの網目は思いのほか小さく、まっすぐに足をひっかけられない。少年が、ちょっと斜めに足の甲をひねると、丁度いい具合に足先がフェンスの穴に納まった。 なぜ、人は飛び降りる時、靴をそろえて置くんだろう?などと、フトどうでもよいことが少年の脳裏をよぎる。だが、そんな思考はすぐにかき消された。今度は、右手でフェンスをつかみ、左足をかけてみる。ゆっくりと、そして着実にフェンスをよじ登る少年。人一人の重みに耐えかねるのか、悲鳴をあげるかのように、やたらとフェンスがきしむ。 (遺書は用意した、僕をいじめた奴らの悪行をしたためた日記も用意した。ハデに死んでやる。だってこれでホントに最期だもの、やられっぱなしの僕が最後にできる復讐。みんなほえづらかくなよ。街の一等地のビルから飛び降りてやる。) 少年の目がギラギラと怪しげな光を放つ。 しかし、フェンスの7合目にまでたどり着いた時、少年は突如、背中に妙な居心地の悪さを感じ、振り返った。すると、そこには一人の男が壁を背もたれに、けだるそうに足を投げだし、たたずんでいた。紺色のスーツを身に纏った男は、コーヒーのアキ缶を灰皿代わりにタバコをふかしている。そうして、ここからがちょっとおかしい。そう、男は眉一つ動かさず、少年の動向を眺めているのだ。ギョ!っとした少年は思わず叫ぶ。 「なに見てんだよ!止めようとしても無駄だぞ。僕の決心は堅いんだ!」 声がちょっと上ずってしまった。まさかこんな時間、こんなビルの屋上に誰かがいるとは思ってもみなかったのだ。少年は動揺を隠せない。けれど、その反面、男は不自然にも、イヤにおちついた様子で口を開く。 「いや・・・止めやしないよ。ただ見てるだけ。」 そう言うと、タバコの吸い口を口元に運んだ。男はタバコの煙がけむいのか微かに目を細める。 (こんな時にちゃらけてるのか?) 少年は、予想だにしなかった男の返事に思わず煙に巻かれそうになるが、真っ赤な顔で、必死に切り返す。 「僕は本気だぞ!」 「・・・だろうな。」 ゆったりとした男の間。あくまでも淡々とした男の言葉に、少年はやや拍子抜けをする。フェンスに食いたてられていた、指がゆるみはじめた。少年の怪しげな眼光はすっかり消えはじめる。 「冷静だね、おじさん。ふつー・・こういう時は、止めるよ。」 「・・・だろうな。」 「なんで止めないの?」 「・・・だって、本気なんだろ?」 妙にシビアな話題にも関わらず、しれっと言ってのける男。男との会話の数に比例して、少年の顔に血色がもどりはじめた。張り詰めたオーラがゆるみ、次第に現実に引き戻されはじめたのだ。 「それは、そうだけど・・・・」 「そうだろうよ。なんだか昔の俺を見ているようだ。若い頃、そんな風に俺もビルのフェンスをまたごうとしたっけな?って思ってさ。」 「おじさんも!」 男の言葉に突如、瞳を輝かせ、フェンスをするすると降りてくる少年。 「まぁね、けど、おじさんはよくないな、俺はまだ、36歳だし。」 「僕から見たら充分おじさんだよ。けど、なんで、おじさんは死のうと思ったの?」 少年は男の横におずおずと、そしてちょっとだけバツが悪そうなテレ笑いを浮かべ、腰を下ろす。白いソックスの足裏が、すっかり屋上のホコリやら土やらですすけてしまっている。 「多分、お前と似たようなもんだよ。10台やそこらで自殺を決意するっていやぁ、受験だとか、いじめだとか、コンプレックスだとか、失恋だとか、夢への挫折だとか、親との軋轢だとか、自分に対する無価値感だとか・・・よくあることだけど、けど、なんだか自分一人だけ追い詰められてるような気がするんだよなぁ・・・あの頃は・・・」 寂しげな目をし、男の横顔を見つめる少年。やがて、男が全くの初対面にもかかわらず、少年は、ぽつりぽつりと飛び降りようとしたワケを語り始めた。そうして、全てを語り終える頃には、泣いていた。泣き顔を見られるのが恥ずかしいのか、少年は顔を覆い隠すように両膝を抱え込んで、嗚咽をあげる。 「死にたくないよ・・・僕だって死にたくない・・・だって、まだやりたいことだっていっぱいあるし・・・」 喉の奥から絞り出すように語る少年。声が少しぐもっている。 「じゃあ、死ななきゃいいじゃないか。」 そう言いながら男は、指先で2、3度タバコをはじき、アキ缶の小さな入り口に器用に灰を落とした。缶の底に残ったコーヒーに灰が落ち、みるみる水気を吸い取ってゆく。 「でも、僕、もう高校辞めちゃったし・・・大学にも行けないし、きっとこんな僕は、大人に成っても、なかなか会社で雇ってもらえないし、僕の人生はもうお終いだよ。僕は人生の落伍者なんだ。」 少年の言葉に、ちょっとだけあきれた顔をしながら男は言う。 「子供の癖に、落伍者だなんて難しい言葉、よく知ってるな。」 「当たり前だよ、こんなの誰でも知ってることだよ。」 少年は、しゃくり上げながらも憎まれ口を叩く。男は小さくため息をついた。 「人生80年、人間の寿命も随分延びたもんだ、こんな無間地獄が延々続くかと思うと、子供でなくったって、生きているのが嫌になることもあるだろうよ。」 ぼんやりと宙を見つめ、誰に語るでもなくつぶやく男。少年はそれを黙って見つめる。 「お前、知ってた?この日本じゃ、1年間に3万人も自殺するんだってこと。」 男の言葉に少年はクビを横に振る。それを見終えると、再び男は独り言に戻り、くゆる煙とともに、しばし感慨にふけりはじめた。 「長すぎるんだよなぁ・・・人生って。」 そう言うと、男はわざと勢い良く煙を吐き出した。二人でしばらく雲ひとつ無い空を見上げていた。やがて、男はまだ少しだけ長いタバコの吸殻を缶の黒い穴に突っ込むと、何かを思い立ったように立ち上がる。今までとは打って変わって明るい口調だ。逆光を浴び、少年を見下ろしながら言う。 「よし!お前に一ついいことを教えてやるよ。お前の人生にタイムリミットを作ってやろう。お前、年はいくつだ?」 「17歳」 「じゃあ、10年後の、27歳だ。」 不思議そうに見上げる少年に、男は笑顔で手を差し伸べてくる。 「俺と約束しろ、これからの10年間、お前は前向きに生きてみろ。何も考えず、自分の出来ることを、ただガムシャラにやるんだ。ハンパに自殺未遂なんかするな、とにかく何かをやれ、常に前向きに。嘘っこでも演技でもなんでもいいから、前向きにだ。そうして、27歳の今日という日を迎えて、それでも死にたいなら、もう死んでいい。10年経って、たとえお前が自殺しても、俺はお前の人生に喝采を送ってやる。」 そして、10年後に同じ時刻、同じ場所で落ち合う約束をして、二人は別れた。 |
(「あした(下)」げ続く)